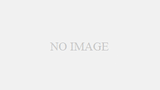音楽雑記。
過去に日記に書いたものを再掲したものです。
常々思うのですが、音楽ってそれだけじゃ成立していません。
その音楽から思い浮かべる情景、苦労、感動があるから成り立っています。
現に、西洋音楽と無関係に育った人達は「ドミソ」(長調)と「ラドミ」(短調)からくるイメージ・感情というものが沸かないらしいらしいですし。
いくら「ドミソ」の基音の周波数比が~云々いっても、「なぜそれを聞いて明るいと感じるか」は科学的には証明されていません。
そういう「音(和音)」と「経験」が結び付けられてるから、という説が一番もっともらしいと思っています。リズムも同じ。
それを踏まえた上で。
やっぱりゲーム音楽でも、苦労した場面とか長い時間を共有した曲というのは
(もちろん曲自体の良さが必要ではあるものの)すごく心に響くものがあるわけです。
共有した時間が長い、というのがかなり重要で、モチーフが繰り返し用いられる、あるいは
単純に短いループを延々と聞いてる、というのも「記憶・思い出」という要素が大いに関わってより良い曲に聞こえるわけです。
そういう意味で、昔のゲームは(意図はしていなかったものの)印象に残りやすく、有利。
GBテトリスとか、やった人はみんな音楽覚えてるし、超懐かしくて「やりたい!」って思うでしょ。
どう考えても最近のゲームの曲の方が音楽的に高い位置にあるものが多いのに、それは理解されにくいわけです。
いや、音楽に限らずゲームそのものもなんですが。
「音楽そのものがいい」というのは、それだけ西洋音楽を聞いてる人だから感じられるんですよね。多くの人にそれを求めるのは難しい。
で、これらの文脈とはちょっとズレたことを。
はっきり言うと、苦労が何もなかったゲームの音楽は、私の印象に残りません(´・ω・`)
ロマサガとか絶対、ボスが強いから曲が映えるのだと思ってます。
曲だけ聞いても、「こんなんオレでも作れるじゃん」とか思っちゃう。実際、複雑なことをしている音楽では、ない。でも名曲認定。
そこに、「死闘があった」という記憶があるから。
カルドセプトサーガとか、曲だけで言えば壮絶なバトル曲がたくさんあるのに
ボードゲームってだけで、ちょっと浮いてる感がある。
っていうか「ボードゲーム1面最初のバトル」からあのテンションはありえんw 何度でも言う。ありえんwww
参考動画→http://www.nicovideo.jp/watch/sm198238
世界観が違うと言っても、桃鉄でいきなりこんなの流れたら腹いたい。
でも、こういう現象があるからゲーム音楽が悪いとかそんなことを思うことは全くなく、むしろ長所だと思っています。
そもそもクラシックだろうとクラシック風だろうと、時代やその背景、歴史があるから名曲と言われるものがあるわけであって
音楽そのもののレベルだけで言えば、現代人ならずっと昔の偉人と同等以上の曲がいくらでも作れるはずです。
でも、それだけじゃ埋もれてしまうんですよね。
曲の良しあしだけじゃ、やっぱりなかなか難しいんです。少なくとも、私には何かが足りない。共有する経験と時間が必要。
曲そのものに惹かれたものも確かにいくつもありますが、全体からの割合でいえばやはり少ない。
ちなみに、この雑記で主張したかったことは結局書いていません。その体も成してないし。
あと楽器フェア行きたい。
音楽と体験
 音楽
音楽